|
[ 土木学会選奨土木遺産 ]
|
|
|
|
|
|
|
|
阪堺電気軌道
|
|
|
阪堺電気軌道(通称:阪堺電車)は、大阪市の恵美須町ー堺市の浜寺前間を結ぶ阪堺線(14.0km)と、
|
|
|
大阪市内の天王寺駅前ー住吉間を結ぶ上町線(4.3km)の2路線を有する、軌間1,435mmの民営の路面
|
|
| 電車鉄道である。 |
|
|
|
|
[ 歴史 ]
|
|
|
|
|
・ 1897年(明治30年) 大阪馬車鉄道株式会社設立
|
|
|
・ 1900年(明治33年) 天王寺南詰(現在の天王寺駅前)ー阿倍野(現在の東天下茶屋)間(1.7km)
|
|
|
開業(軌間:1,067mm)。 その後、上住吉(現在の神ノ木)まで延伸。
|
|
|
・ 1902年(明治35年) 上住吉ー下住吉(現在の住吉)まで延伸。
|
|
|
|
・ 1907年(明治40年) 社名を、浪速電車軌道株式会社に変更。
|
|
|
・ 1908年(明治41年) 天王寺ー下住吉間の馬車鉄道による営業を廃止。 軌間を、1,067mmから
|
|
|
1,435mmに改軌し、電化・複線化に着手。
|
|
|
・ 1909年(明治42年) 電車運行が開始。(製造電車20両)
|
|
|
|
・ 1910年(明治43年) 阪堺電気軌道株式会社を設立して社名を変更。
|
|
|
・ 1911年(明治44年) 恵美須町ー市之町(現在の大小路)間開業。
|
|
|
| ・ 1912年(明治45年) 市之町ー浜寺(現在の浜寺駅前)間、延伸開業。 |
|
|
|
現在、運用されている車両の中の「モ161形」は、1928年(昭和3年)に製造された車両で、営業中の
|
|
|
車両では日本最古である。
|
|
|
鉄道会社としての歴史的価値が認められ、2018年(平成30年度)に「土木学会選奨土木遺産」として |
|
|
| 認定されている。 |
|
|
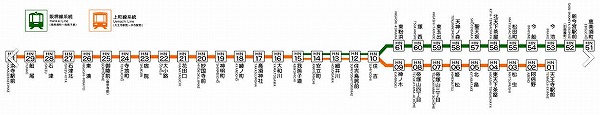 |
|
|
|
|
|
路線図
|
|
|
( 画像をクリックすると拡大して見られます )
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
「土木学会選奨土木遺産」認定プレート
|
|
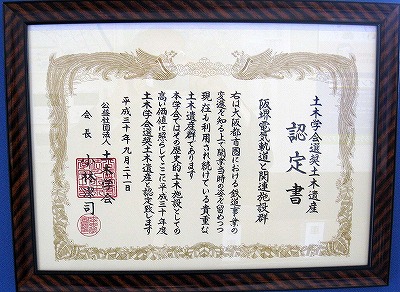 |
|
|
「土木学会選奨土木遺産」認定書
|
|
|
( 画像をクリックすると拡大して見られます )
|
|
|
|
|
|
[ 施設 ]
|
|
|
|
.jpg) |
|
|
我孫子道車庫
|
|
|
.jpg) |
|
|
|
天王寺駅前駅
|
|
.jpg) |
|
|
恵美須町駅
|
|
.jpg) |
|
|
浜寺駅前駅
|
|
sumiyoshi.jpg) |
|
|
住吉停留場
|
|
|
|
|
|
|
( 大和川橋梁 )
|
|
|
|
本橋梁は、阪堺電軌が、1911年(明治44年)恵美須町ー市之町間の開業時に架設されたもので
|
|
| 橋長:198.57m、9径間(18.288m+21.336m×7連+18.288m)の下路式プレートガーダーである。 |
|
|
橋脚も、鉄パイプ製である。
|
|
|
|
|
|
.jpg) |
|
|
阪堺電軌・大和川橋梁全景
|
|
|
.jpg) |
|
|
|
大和川橋梁路面 (右岸より)
|
|
.jpg) |
|
|
橋梁を渡る電車
|
|
|
kyokyaku.jpg) |
|
|
|
鉄パイプの橋脚
|
|
plate.jpg) |
|
|
製造プレート
|
|
|
|
|
|
[ 車両 ]
|
|
|
|
(2022年現在現役中の車両)
|
|
|
( 撮影時期によりラッピング塗装は異なります)
|
|
(R4-1-7).jpg) |
|
|
|
|
モ161形(161号)
|
|
(H25-4-23).jpg) |
|
|
モ351形(351号)
|
|
(H25-4-23).jpg) |
|
|
モ501形(502号)
|
|
(H25-4-23).jpg) |
|
|
モ601形(601号)
|
|
(2013.2.17).jpg) |
|
|
モ701形(701号)
|
|
 |
|
|
モ1001形(1001号)
|
|
(2022.1.7).jpg) |
|
|
モ1101形(1101号)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|